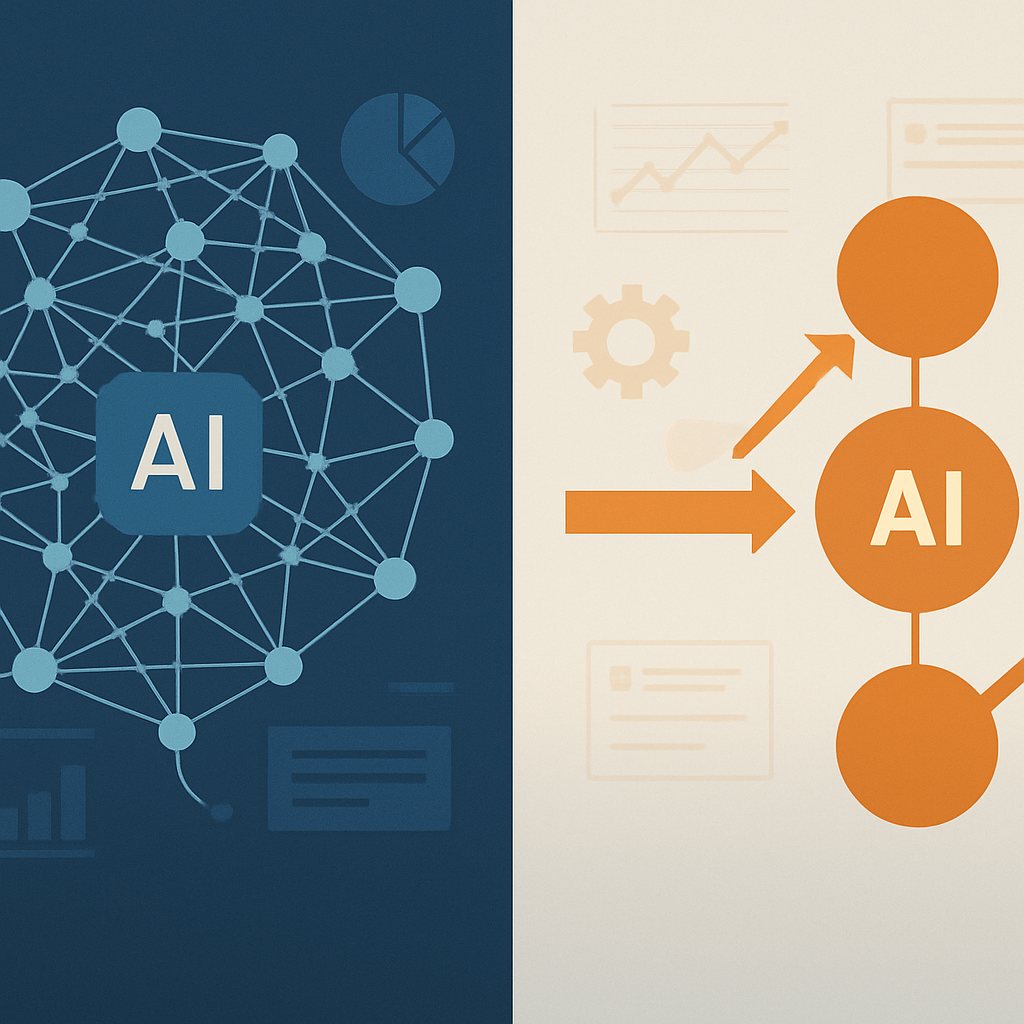音声で聞かれる方はこちら↓
短い音声ですので、気楽に聞いて下さい。
会話の文字起こしはこちら↓
マーケティングの本当に重要なポイントを押さえてください。

皆さん、こんにちは。「AI最前線」へようこそ。AI研究者の佐藤です。
こんにちは。企業のAI導入を現場で支援している田中です。博士、今週もAI業界は騒がしかったですねぇ。OpenAIから「ChatGPTエージェント」が発表されました。


ええ。ユーザーがね、こう…指示を出すだけで、AIが自律的にブラウザを操作して、
はい。


リサーチから、まあ資料作成までこなすっていう…まさに「動くAI」なんですよ。 SFの世界がまた一歩、現実に近づいた感じがしますね。
「寝てたら仕事が終わる」なんていうキャッチフレーズで紹介されてましたけど、


ええ。
私も早速、その実力を検証した動画を食い入るように見ましたわ。 博士、技術的な観点から見て、このエージェントの仕組みって、どうなってるんですか?


はい。えーと、技術的には非常に野心的でしてね。
ほう。


ブラウザ操作、画面の視覚的な理解、それからコード実行といった、複数の…ええ、異なるツールを、一つのシステムに統合してるんです。そして強化学習によって、
うんうん。


AIがタスクに応じて、こう…最適なツールを自ら選んで使うように訓練されている、と。
なるほど…「理論上は」すごそうですねぇ。


ええ。
ただ、動画での検証結果は、正直…期待外れでした。ある企業についての分析レポート作成を頼んだら、


ああ、はい。
20分も待たされた挙句、出てきたのはほとんど白紙の資料やったと。


ええ、そこがまさに今回の核心です。
やっぱり。


理論と現実の間に、まだ大きなギャップがある。技術的に言うと、複数のツールを連携させる際のオーバーヘッド…つまり、
オーバーヘッド。


そう、「段取り」に時間がかかりすぎてるんですね。例えるなら、そうですね…ネジを一本締めるだけのために、
はい。


家にある工具箱をぜーんぶ、丸ごと現場に運んで来ちゃってる、みたいな状態なんです。非常に、非効率なんですよ。
その「工具箱」の例え、めちゃくちゃ分かりやすいですわ。一方で、同じタスクをやらせた「Manus」という競合ツールは、


ええ。
短時間で見事なレポートを完成させてました。この差は一体何なんでしょう? 現場からしたら、月額200ドルも払って白紙が出てくるなら、時給1500円でパートさんを雇った方がよっぽどマシですよ、ほんまに。


的確なご指摘です。Manusは、おそらくですが、タスクに特化した軽量なモデルを使っているんでしょう。
ああ、なるほど。


OpenAIの「何でもできる万能な工具箱」とは対照的に、Manusは「レポート作成に特化した必要最小限の道具セット」を、まあ、用意している。だから速くて、結果の質も高い。
ほうほう。


まさに現場主義のアプローチですよね。
しかもManusにはあって、ChatGPTエージェントにはない決定的な機能がありますよね?


と、言いますと?
「定期実行機能」です。毎日同じ時間にニュースをまとめてレポートを作らせる、みたいな。これがないとビジネスの現場では致命的ですわ。


その通りです。大企業は、やはり倫理的な懸念から、
はい。


ユーザーが知らない間にAIが勝手に動き続けるような機能の実装には、慎重になりがちです。その隙を、より機動力のある競合が突いている、と。そういう格好ですね。
なるほどなぁ。現場では「3ヶ月ルール」っていう言葉がありましてね。


3ヶ月ルール。
ええ。導入したツールが3ヶ月以内に明確な効果を出せないと、もう誰も使わなくなるんです。 特に問題なのが「責任の所在」。AIが「この経費は承認できません」って判断したとして、


うん。
部下から「なぜですか?」って聞かれた上司が「いや、AIがそう言ってるから」では、もうマネジメントが成り立ちません。


それは「Human-in-the-loop」、つまり人間がプロセスに関与して、
はい。


最終的な意思決定権を持つ、という設計の重要性を示唆していますね。Manusは処理の工程が見えるから、
そうそう!


ユーザーは「今、何をしているか」が分かって安心できる。対してChatGPTエージェントの20分間の、あの「ブラックボックス」処理は…
ええ…。


現場に不安と不信感を与えてしまうわけです。
まさに!現場は「人間を排除する全自動化」なんて求めてるんやなくて、


うん、うん。
「面倒な作業をAIに任せて、人間にしかできない判断に集中したい」、ただそれだけなんです。博士、技術者の方から見て、


はい。
OpenAIは、この「地味やけど実用的な改良」に舵を切れると思いますか?それとも「美しい統一アーキテクチャ」みたいな、こう…技術的なプライドが邪魔をしますかね?


うーん…率直に言って、すぐには難しいかもしれません。
あー、そうですか。


研究者というのは、どうしても…論文映えするような、革新的な技術を追い求めがちですから。しかし、田中さんのクライアントのような企業が月額200ドルの契約を次々と解約し始めれば、
ええ、ええ。


財務的な圧力から動かざるを得なくなるでしょう。私の予想では、3ヶ月から半年以内に、
ほう。


何らかの軽量版、あるいは実用性を改善したアップデートを発表する可能性は、十分にあると思います。
半年ですか…。


ええ。
その頃には、市場はManusのような実用的なツールにかなり奪われているかもしれませんねぇ。うちが支援している企業様には、


はい。
もう「様子見は終わりです。今すぐManusで小さく始めて、成功体験を積み重ねましょう」とアドバイスしています。一度「使えない」っていう烙印を押されたツールが、


ええ。
現場の信頼を取り戻すのは至難の業ですから。


合理的な判断だと思います。「組織の記憶」というのは、本当に恐ろしいもので、
ほんとですよねぇ。


一度の失敗体験が、そのベンダーへの不信感を何年も根付かせてしまいますからね。いやぁ…今日の議論で、技術の理想と、現場が求める現実との間にある深い溝を、改めて痛感しました。
いえいえ、こちらこそ。技術的な背景がクリアになって、現場での判断に自信が持てました。結局、AIもただの道具。


ええ。
使いやすくて、確実に仕事が楽になるもんが選ばれる。当たり前の話ですわ。


全く同感です。さて、本日の議論はここまでとしましょうか。
最後に、リスナーの皆さんへ一つ、問いかけをさせてください。


はい。
あなたがAIに仕事を任せるとしたら、どちらを選びますか?「時間はかかるかもしれないけれど、いつか完璧な仕事をこなすかもしれない、完全自動の天才」ですか?それとも、「完璧ではないけれど、速くて確実で、あなたがいつでも手助けできる、優秀なアシスタント」ですか?あなたの仕事の未来を、少しだけ想像してみてください。それでは、また次回。「AI最前線」でお会いしましょう。